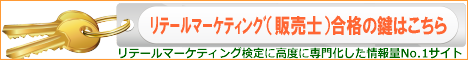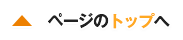公務員試験は1本に絞らない
 公務員試験の場合、職を見つけることが前提ですから、就職試験と同じような考え方を用いて目指す公務員試験を決めていく必要があります。
公務員試験の場合、職を見つけることが前提ですから、就職試験と同じような考え方を用いて目指す公務員試験を決めていく必要があります。
そこで、まず1つに絞るのは回避することが重要です。
中には、警察官1本狙いという人もいますが、警察官になりたいのであれば、地域を限定しない限り、いくつも試験を受けることができます。
例えば、自分が現在住んでいるあるいは実家故郷の県警(道警、府警)と警視庁(東京)を合わせて受験することができます。これは、消防官であっても同じことです。
中には、国税専門官ような特殊な職種を狙っている人もいると思いますが、公務員になりたいのか、国税専門官として働きたいのか、動機はいずれかになると思いますが、この場合であっても試験の内容が似ている国家公務員Ⅱ種などの併用を視野にいれた方が良いでしょう。
これは、公務員になりたい、という人が圧倒的に多いため、いわゆるリスクを回避するための考え方です。公務員試験を目指す人は、一般的に公務員になりたいという考え方を持っている人が大多数で、どうしてもここが良い、という限定的な考え方を持っている受験生は少ないように思います。
事実、国家公務員の場合、例えば経済産業省に行きたいと思っても、経済産業省に入省するためだけの試験はありません。省庁関係なく、国家公務員試験の行政職を受験することになります。そして、その合格をもって省庁周りを行うというプロセスになります。
ほとんどの場合は、省庁の説明会への参加や訪問の段階で入りたい省庁を決めますから、最初から限定した省庁を狙う人はあまり多くありません。
また、公務員試験はある程度の試験慣れも必要で、その意味では複数の試験を受験することでその感覚を養うことができるようになります。公務員試験は受験料がかかりませんから、いくら受けても交通費以外のお金はかかりません。
だとすると、無料で本試験を経験でき、その経験を次の試験で活かすということもできます。ですから、最も重要視する公務員試験をまずは決めておいて、その本試験以前に実施される公務員試験を腕試しに受験してみるという戦略が考えられます。そして、両方合格すれば、あとはどちらに行くのかは合格してからじっくりと考えれば良いでしょう。
多くの受験生の場合、少なくても2~3つの公務員試験を受験するようです。中にはもっと多く受験する人もいますが、合格しても自分が勤める気がない公務員試験を受験することは無意味ですから、少なくてもリスク回避という意味では、合格したら働くことを前提に選ぶのが良いでしょう。
国家公務員を基準に考えるのが最適
複数の公務員試験に照準を合わせて勉強するとしたら、国家公務員をまずは狙うという方針を立てることをオススメしています。
その理由は、まず国家公務員試験は必ず試験の実施が毎年行われ、そして採用がされることです。地方公務員試験の場合、年度によっては採用がないこともあります。
もうひとつは、国家公務員試験の勉強内容が地方公務員試験の勉強内容のベースになっていることが多いためです。ベースと言うよりも、基本的に行政職であれば国家公務員試験も地方公務員試験もその内容に大差はありません。
どちらかと言うと、問題のレベルは国家公務員の方が若干高い傾向がありますので、国家公務員を目指していけば地方公務員の勉強にも同時に対応することができるようになります。
以上の2点を考えると、年齢制限などに問題がない場合は、国家公務員(Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種)を軸足として設定して、さらに地方公務員試験を狙っていくというのが理想的な組み合わせだと思います。
これは行政職を基準に考えましたが、専門系の職種でも国家公務員を勉強のベースに考えると良いと思います。たいていは、国家公務員の勉強内容にプラスアルファの専門分野が追加されるだけですから、勉強内容としてはそれほど差がありません。
公務員試験の合格を目指すためには、国家公務員試験を受験することをまず設定する。その上で、それに合格できるような勉強内容と勉強方法を考える。これが基本です。こうすることで、地方公務員試験にもほとんど自動的に対応できるようになります。
公務員試験に合格するためのポイント
初めての方へ
当サイトは膨大なコンテンツがあります。超高確率合格法では短期合格のノウハウを紹介していますので、全てお読みになることをオススメします。
公務員や販売士検定を狙っている方は、そのままコンテンツページを参照していただいて大丈夫です。
サイトの全体像はサイトマップを参照してください。