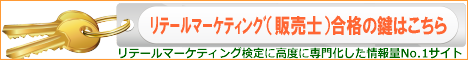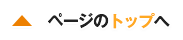本試験で回答できるように普段から問題を解く
 問題にはいくつかの種類があります。詳細は、問題の優先順位で述べていますが、最も重視すべき問題は過去問題です。
問題にはいくつかの種類があります。詳細は、問題の優先順位で述べていますが、最も重視すべき問題は過去問題です。
資格学校の講座を受講していれば、過去問題集は通常その講座の教材一式の中に含まれています。過去問を見るタイミングは早ければ早いほど「敵を知る」という意味でも有用です。
しっかりとした資格学校であれば、過去問の重要性は認識していますから、過去問は学習初期の段階で配布されるはずです。仮に配布されないとしたら、金銭的には負担になりますが、別途自分で購入しておきたいところです。
ただし、資格学校が「過去問題集」というタイトルの問題集を配布しない場合でも、その資格学校が配布する問題の中に、過去問題が組み込まれている場合も多いです。この場合、資格学校の問題集を解いていくことで、自分が気づかないうちに過去問題をやっていることになります。(これはこれで良いのですが、できれば自分がやっている問題はどういう種類のものか事前に把握しておいた方が良いです)
問題を解く流れについては、一般的な方法と何ら変わりません。
講義を聴く
↓
問題を解く
この流れです。聴いた講義に対応する問題を解いていく。この繰り返しが基本的な勉強スタイルとなってきます。最近の資格学校は、テキストと問題集が完全リンクしており、例えば1回目の講義を聴いた後に、1回目の講義に対する問題、というような形でテキストと問題集と講義が一体的に構成されているものも増えています。
問題に関しては、通常であれば「問題集」と「過去問題集」が分けて配布されます。難関系の資格試験になると「問題集」は「基礎問題集」「応用問題集」などと細分化していくこともありますが、基本的な構成としては、スクール独自の「問題集」と「過去問」がメインです。
一般的には、いきなり「過去問」にあたるのは難易度が高いので、まずは「問題集」で実力をつけたりしながら、徐々に「過去問」を見ていくようなスタイルとなっています。しかし、高確率合格法ではいきなり「過去問を見る」ことを推奨しています。
問題は解くよりも「見る」
さて、問題はどう解いていくのが良いのでしょうか?目的は、その問題が本試験に出題された時に、確実に答えられるようにすることです。
そのための方法としてはいろいろありますが、問題を覚えてしまうのが手っ取り早いです。資格試験合格のためには、本試験で解答用紙に正答を埋めることができることが絶対条件です。これ以外に合格のために必要なことはありません。どんなに努力をしても、その過程が評価されることはないのです。
具体的な問題の解き方ですが、まずは、何を求めれば良いのか?を探ります。つまり、解答箇所(欄)を一番最初に見ます。択一試験ならば、○を探すのが×を探すのか。数字を入れるのならば何の数字を入れるのか。語群を選ぶならば、語群を一通り見ます。
続いて、解答欄から逆算するような気持ちで、問題文全体を俯瞰します。この時に大切なのは、問題そのものが学習内容全体のどこの位置づけにあるものかということを把握することです。これをしない限りは、項目や論点にいきなり入り込んでしまい、非常に苦悩を強いられます。
何をやらせようとしているのか、何を要求してるのか、学習内容全体の中でどこの位置づけにあるのか?ということを中心に問題を読んで(いわゆる素読)いきます。ここがポイントです。解くのではなく、読むのです。
過去問を後回しにする理由は、たいていの場合「難しいから」というのが中心です。なぜ難しいのかと言うと、解こうと思っているから難しいのです。資格試験では問題が解けない限り合格は出来ませんが、それは本試験だけの話です。今の時点で解けないからと言って合格できない、ということではありません。最終的にそのような状態になっていれば良いと言うことです。
問題が解けないことによって、多くの受験生がやる気をなくし、自分には合格は無理だ、と思い込んで挫折するケースが多いです。これは、問題を解こうと思っている→解けない→ダメだ、という連鎖によるものと推測されますが、そもそもそんなに簡単に問題が解ければ誰も苦労しません。仕事を辞めて勉強に専念する必要も、資格学校に通う必要もないのです。
高確率合格法は、そんなに簡単に問題は解けない、という前提から出発します。ですから、プレッシャーもありません。できないことを前提に、どうすればできるようになるのか?というアプローチをとります。
まずは問題を読む、これがポイントです。解けないものを解こうとしても、やる気がなくなってきます。今はまだ解けなくて良い、それよりも「どういう問題が、どういう視点で、どういう問われ方で出題されているのか」という観点で問題を読む、そのことが重要です。
問題が解けるようになるかどうかの鍵は、反復が鍵になってきます。今の段階では、問題の傾向などを把握することの方が重要です。
ですから、とにかく問題を読む。そして、「なるほど、こんな感じで本試験では問われるのか」と思う。そして、解答を見ます。解答解説を見て、どう答えるべきだったか?を考え、そしてまた納得します。その時に、解答解説が不親切又はまったく意味が分からない場合には、テキストに戻って調べます。
最初はこの作業を行うだけで相当時間がかかるはずです。「読む」という作業はそれほど単純なものではありません。しかし、この「読む」という作業を繰り返し行っていくことで、必ず問題が解けるようになります。
この作業は、「問題集」と「過去問題」ともに行ってください。順番は「問題集」→「過去問」の順です。この順で進めるとそれほど抵抗なく過去問を読むことができます。また、できるだけ講義直後に行った方が良いです。そうすると、講義の記憶が残っていますので、スムーズに問題を読むことができるようになります。
繰り返しますが、勉強初期の段階で問題を「解こう」とすると挫折します。理由は解けないからです。ただし、解けないのは当たり前ですから、解けないことを前提に問題を「読む」ようにしてください。経験的に、同じ問題を4~5回読むことができれば、その問題は必ず解けるようになります。
高確率合格法の基本
初めての方へ
当サイトは膨大なコンテンツがあります。超高確率合格法では短期合格のノウハウを紹介していますので、全てお読みになることをオススメします。
公務員や販売士検定を狙っている方は、そのままコンテンツページを参照していただいて大丈夫です。
サイトの全体像はサイトマップを参照してください。